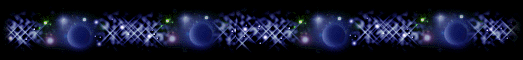|
『明日の夜、麗しき蒼き宝を頂戴しに参上いたします・・・T』
こんな一文が書かれた淡いラベンダー色のカードが、都内のある邸宅に届けられたのは、寒さの厳しい2月の半ばのことだった。
「・・・・がぁぁっ!!!この気障ったらしいカードっ! 何度見ても腹が立つわっ!!」
「・・・なら、そんなに何度も読み返さなければいいじゃないですか、坂本警部」
「うるさいっ! つい見てしまうのだから仕方がないだろうっ! それというのもこの部屋がキラキラしていて落ちつかないせいだっ!」
「・・・警部、それは完全に八つ当たりです。それをそんなに大きな声で・・・丸聞こえですよ・・」
「おお、それがどうした!?
」
何が悪いのかよくわからずに眉を寄せている坂本警部に、桂警部補は額を押さえてため息をついた。
「・・まぁ、確かに落ち着かない部屋だけどね」
小さく肩をすくめて桂が小さくつぶやく。
彼らが座っているのは、カードが届けられた狩野家のリビングの中央に設えられた、紺色のビロード生地に金糸銀糸で見事な刺繍がほどこされている豪華としか言いようがないソファーである。
30畳はありそうな室内の、足下には臙脂色を基調としたペルシャ絨毯、頭上には見事なまでに輝く大きなシャンデリア。しかも部屋の至る所に、どこかの鑑定番組に出品したら高額鑑定まちがいなしであろう絵画や西洋アンティーク調の華やかな家具、装飾品がずらりと並んでいる。
彼らから少し離れたドアの脇には、先程これまた豪華なティーセットで紅茶を運んできた若いメイドが控えており・・・その肩が笑いをこらえるように震えているように見えるのは・・・桂の気のせいではないであろう。
「それよりも桂・・この『宝』について何かわかったか」
声を潜めて尋ねた坂本に、桂は顔を近づけてさらに小さな声で答えた。
「ええ、先程連絡がありました。『蒼き宝』・・とは、この狩野家の女主人が所有する80カラットのサファイアペンダントのことだと思われます」
桂の言葉に、坂本はこの屋敷に来る前に見た資料の中にあった、華やかな女性の顔を思い出した。
「う〜〜ん、この不景気にそんなものを持っているのか、あの女。ビューティーサロンの経営というものはそんなに儲かるのか?」
「さあ。ただ、そのペンダントの出所が不明瞭で、十条君がさらに現在調査中と・・・」
桂が続けようと口を開いたとき、二人が入ってきたドアと反対側にあるドアが静かに開いた。
「お待たせして申し訳ありません」
姿を現したのは、ゆるくウェーブした長い栗色の髪と同じ色の、意志の強そうな瞳が印象的な美しい女性・・資料の中にあった狩野家の女主人だった。
慌てて立ち上がった二人の方に優雅に近づき、彼女は大理石のテーブルを挟んだ向かい側にそっと腰を下ろした。身につけている大きく胸元の開いた黒いワンピースが彼女の見事なプロポーションを際立たせている。
ギクシャクと再びソファーに座った坂本の後ろに回って立ち、そのまま桂はその女性を観察した。
『狩野美和子・・か。未亡人にして資産家狩野家の女主人。自身もモデル界から全国規模のビューティーサロンの経営者として成功した、美容界のカリスマとしてメディアからも注目される・・・と。確かに見た目は俺の母親と同じ年代とは思えないな・・』
来訪前に頭に入れたデータでは、彼女は今年49歳になるはずだ。息子と娘は既に成人しており、都内でそれぞれ自由な生活を楽しんでいる。この広い屋敷には美和子と、彼女の秘書を長年務めている、柿崎という初老の女性が住んでいるだけである。
美和子が座ると同時に、テーブルにティーカップが置かれ、すぐにメイドが部屋から姿を消した。それをちらりと見てから、美和子が口を開いた。
「警察の方ですわね。私が狩野美和子です」
「私は警視庁捜査一課の坂本警部、こちらは桂警部補です」
軽く頭を下げた桂に一瞬だけ目をやり、美和子はすぐに坂本に視線を戻した。
「それで、その気味の悪い手紙は何ですの?」
眉をひそめてテーブルの上に置いていたラベンダー色のカードを一瞥する。
「この『T』という者からの予告状・・と思われますが」
「そんなこと、見ればわかるわっ!」
坂本のズレた返事に、美和子が美しい眉を上げて声を荒げた。
「 私が言っているのは、たちの悪い悪戯じゃないかということよっ! 気味が悪いから一応警察に連絡しましたけど、こんなものを送ってくるなんて常識では考えられないでしょうっ!!!」
「はぁ・・それはそうですねぇ・・」
声を荒げることなど滅多にないであろう、この上品そうな女性をここまで逆なでできるとは、坂本の一種の才能かもしれない・・。
桂は思わず頭を抱え込んでしゃがみ込みそうになるのを、なんとか耐えて口を開いた。
「表沙汰にはなっていませんが、最近同じように予告状が届けられて、その予告通りに物が盗まれるという事件が続いています。この手紙も、文面や使われている紙などから見て、同じ犯人のものだと思われます」
「・・ということは、警察は今までその犯人が何をいつ盗むかわかっていて、捕まえられなかったというわけね。・・・随分悠長なこと」
「!」
美和子の嫌みに反応した坂本が思わず立ち上がりかける。その肩を桂の手がぐっと押し止めた。
「・・・」
何とか怒りを抑えた坂本の肩を、今度はポンッと小さく叩くと、桂は美和子に視線を戻し、いかにも困った、という表情を浮かべた。
「それを仰られると我々も耳が痛いです。・・・ですが、今までの件でもそうなのですが、この予告状も『何を盗む』のかはっきり書かれていません。そして・・予告状を送られた被害者が、みなさん揃って『何のことかわからない』と仰っています。本当に知らないのか、我々には教えたくないのかわかりませんが・・・。とにかくこれでは警備のしようもありませんし、予告の日が過ぎても、結局被害者から正式な被害届がでないので、我々警察もどんな手口が使われたか、それどころか本当に何かが盗まれたのかどうかさえ、知ることができない状態なのです」
説明を聞くうちに、美和子の顔がわずかに強ばったのを、桂は見逃さなかった。
「今回の予告状も何を盗むつもりなのか具体的にわかりませんし・・・」
桂と美和子の視線がぶつかる。
「・・・狩野さん、この『麗しき蒼き宝』というのに・・お心当たりは?」
「・・・全くありませんわ」
ゆっくりと美和子が言葉を返した直後、小さくドアがノックされた。
「奥様、明日の打ち合わせのお時間ですが」
「・・・すぐに行きます」
現れた秘書の柿崎に言うと、美和子はすっと立ち上がった。
「そういうことで・・私には身に覚えのないこと。このおかしな怪盗まがいの人の勘違いのようですわね」
「本当に?」
桂の言葉に、一瞬美和子は視線をきつくしたが、くるりと背中を向けて歩き出した。
「ええ。警察の方ももうお帰り下さい。私、いろいろと忙しいんですの。これ以上無駄なお話をしている時間はありません」
そのままドアの所までくると、美和子は二人を振り返った。
「もし・・何か被害があったなら、またこちらからご連絡いたしますので・・では失礼」
介入は無用と暗に示して、美和子はドアの奥に姿を消した。そして広いリビングには桂と坂本だけが残された。
「・・・・なんだ、何なんだっ!あの女はっ!!」
「・・・坂本警部、声が大きいですよ」
「お前は腹が立たないのかっ!! あの女、完全にこちらを馬鹿にしていたぞっっ!!! 」
「・・落ち着いてくださいって。とにかくここを出ましょう」
グルグルと唸っている坂本の背を押して、桂は部屋を出た。
「問題のペンダント、80カラットのサファイアペンダント『ブルースノー』は、時価数億円とも言われるお宝で、もともと英国のある貴族が所有していたものだったのですが、10年ほど前に、英国でのパーティーに出席していた狩野夫人に惚れ込んだその貴族が、夫人にプレゼントしたらしいんです」
「あの色香に惑わされたのだな。なんて女だ」
「そんなに綺麗な人なんですか?狩野夫人って」
「確かに資料の写真よりも実物の方がかなり美人ですね」
「美人だろうが何だろうが、私は気にくわないがなっ」
「10年前といえば狩野夫人の御主人がお元気だったころの話ですね。あまり外聞のいい話じゃありません。まぁ、隠しておきたいのは、税金問題が多分にあるのでしょうけど」
「ふん。がめつそうな女だからな」
警視庁内のある会議室。長方形のテーブルが並んだ殺風景なその部屋に3人の男の姿があった。
坂本が憮然とした表情で窓際の席に座り、桂はその後ろの窓にもたれて立っている。ぴりぴりとした二人の雰囲気から、ただならないものを感じていた新人の十条刑事は、ホワイトボードの前に立って、二人をちらちらと見ながら調査内容を報告していた。
そこへ小さくノックがあり、一人の青年が顔を出した。
「遅くなりました。コーヒーをどうぞ。警部は紅茶でよかったですか?」
「ああ、ありがとう。そこに座ってくれ」
同じく新人の板橋猛刑事がカップを全員の前に配ってから、十条が立つすぐ前の席に座った。
「板橋くんは、今回の件については聞いたかい?」
「はい、報告書は読みました。けど・・」
「けど?」
桂の言葉に、言いにくそうに猛が返す。
「えっ・・と。今回のこの件も捜査はできない、ですよね」
「というと?」
「狩野家からは何の届けもでていないわけですし、実際にまだ何か盗まれたわけじゃないですし・・。今までの盗難事件と同じなら、実際盗まれたとしてもまた現場に近寄らせてももらえないだろうし・・」
猛が小さくため息をつく。
この事件・・警察が『怪盗T事件』として捜査している一連の窃盗事件は、非常に特殊なもので警察も頭を痛めていた。
何が『特殊』なのか。
まず、謎めいた予告状が届くこと。そして最初は悪戯だと思われたその予告通りに『何か』が盗まれること。それなのに殆どの被害者から被害届が出されないこと。
つまり、ターゲットにされる物が盗品であったり無申告で相続したものであったり・・すべて被害者が表沙汰にできないような『曰く付きの代物』ばかりらしいのである。
関係者から漏れてくる情報や、裏で流れる情報から『確かにその予告通りの物』がなくなっているらしいことは掴んでいるが、捜査しようにも被害者の協力が全く得られない。
「今回も確かに表立っては動けないでしょう。しかしこれは同一犯によると思われる連続窃盗事件。一件だけでも届けが出ている以上、事件として成り立っていて、我々が動いているわけです」
「その一件もあれだろう、無許可で山ほど拳銃や刀を持っていたマニアのじーさん。自分の無許可を棚に上げて、絶対犯人を捕まえろ、捕まえたらワシが天誅を加えてやるとか騒いでいたらしいな」
坂本の言葉に、桂は小さく肩をすくめると、もたれていた窓から離れ、座る坂本の横に立った。
「板橋くん、十条くん」
「は、はいっ!」
桂は直立不動になった新人二人を、じっと見つめながら口を開いた。
「今、我々はその犯人が明日の夜、狩野家のお宝を狙って現れるという有力な情報を得たわけです。これが犯人逮捕、それが無理だとしても、少なくともその正体を知るために非常に重要なのはわかりますね?」
二人が緊張したまま何度もうなずく。
「そして明日の夜、狩野美和子が経営するビューティーサロン主催の盛大なパーティーが、都内Tホテルで開かれます。多分、彼女はその場で例のペンダントを身につける予定なのでしょう。そしてそれを狙って犯人は会場に現れる可能性が高い。そこを・・・押さえます」
眼鏡を押しあげながら言った桂の言葉に、二人は目を見張った。
「で、でももし、狩野夫人が盗難を恐れて、そのペンダントをつけなかったら」
十条が口を開く。
「ありえますが・・彼女は相当自己顕示欲が強い人のようです。ボディーガードを倍に増やしたとしても、身に付けるでしょう」
「ようは見せびらかしたいわけだな」
「まあ、そうとも言えますね」
「もし身につけたとしても、そんな場所に警察が入れてもらえるでしょうか・・?」
「無理でしょうね」
猛の疑問に、桂はあっさりと返した。
「じゃあ・・」
「もちろん表立っては入れません。だから・・招待客に紛れて、忍び込みましょう」
にやっと笑って言う桂の言葉の意味を、新人二人が理解するのに10秒ほどかかった。
「し、・・・忍び込むぅ〜っ!?どうやってっ!?」
「だ、だいたいそんなこと警察がやって、もしばれたら・・」
理解した途端に青くなった二人に、桂が大丈夫と答えた。
「どうせ狩野家も表沙汰にできない事件なんです。みつかっても公表できませんよ」
にっこりと言う桂に、二人の背中に冷たい汗が流れる。
「とにかく。動かなければどんな情報も手に入りませんからね」
「そうだ!! どんな手段を使っても犯人の手がかりをつかむのだっ!!! さっそく準備にとりかかれっ!!」
「坂本警部・・あなたもさっさと動いてください」
Tホテル。
国賓や政府関係者も頻繁に利用する、都内でも随一の超高級ホテルである。
豪華だが、落ち着いた色合いで統一された玄関前に、次々と高級車が滑り込み、美しく着飾った女性達をエントランスに送り込んでいく。
その、きらびやかな光景のホテル玄関から通りを数本隔てた、とあるビルの地下にある駐車場の中に、一台の白いワンボックスカーが停まっていた。
中には坂本と桂、そして猛が待機していた。
だが・・その3人の姿は、普段とは全く違っていた。
坂本は深い紫、桂はやや光沢のある濃いグレーの、どちらも仕事で着用しているものとは明らかに違う、エレガントな雰囲気のスーツを身に付けていた。このままドレスアップした人々が集っているTホテルのロビーに紛れ込んでいても、全く違和感はないだろう。
そして猛は・・・。
「だから、どうして俺がこんな格好をしないといけないんですかっ!!」
「だから、それは何度も言っただろう。今回潜り込むパーティーが、ビューティーサロン主催の『女性だけ』のパーティーなんだから。男は会場には入れない」
「それはわかってますっ!! 俺が言いたいのは、何で『俺が』ってことですっ!」
「しょうがないだろう。私達の中でドレスが着られるサイズの人間は、お前だけだったんだから」
「だからって、 こんなにごっつい女がどこにいますかっ!!」
「大丈夫、全然ごつくないぞ。すごーく似合っている」
どうやら本気でそう思っているらしい坂本に、顔を赤くして猛が詰め寄った。
「そんなのうれしくも何ともありませんっ!! 大体、うちの課にも女性刑事がいるじゃないですかっ!! 」
「あいにく、連続コンビニ強盗事件と銀行窃盗団の逮捕が重なっていまして、手が空いている人が誰もいなかったんです。こういう場合は自分たちでなんとかするしかないでしょう?」
運転席から振り返って言う桂の言葉に、猛がぐっとつまる。
「ホテルのロビーにいる十条君からの連絡では、会場に入ろうとする男性には、かなり厳しいチェックがはいっているようです。どうやら会場内を見張ってもらうのは、板橋君1人に任せることになりそうですね」
猛の責任感を微妙に刺激する言葉に、猛はそれ以上の文句を言うことができなかった。
「・・でも・・」
「心配ありません。とても可愛いお嬢さんですよ」
「・・・桂警部補っ!! 」
くすっと笑った桂の前で、猛はゆでダコのようになった。
「素材ももちろんいいんでしょうが、普通の成人男性をここまで見事に変貌させるとは、さすがプロですね」
「そういえば、彼女達はいったい何者なんですか?」
猛の質問に、桂は小さく笑った。
今から数時間前のこと。
パーティー当日の午後、先に車で待っているように言われた猛は、警視庁の職員駐車場に向かった。桂に指定されたワンボックスカーを見つけると、勢いよくスライドドアを開け・・・そのまま固まってしまった。
ドアに手をかけて呆然としている猛の顔から、わずか30センチほどのところに、見知らぬ女性の顔が二つ並んでいたのである。
『な・・なんだ、なんだぁっつ!!!』
いきなりなことに声も出せずに硬直している猛を、なかなかの美人二人が車の座席から身を乗り出すようにして、上から下までじぃ〜〜〜っと探るような目で見つめている。
たっぷり1分近くは観察されていただろうか、その女性達は突然にっこりと笑うと、猛の両腕を取り車の中に引っ張り込んだ。
「うわっ!? な、なんだっ!? 」
叫ぶ間もなく後部座席に座らされると、両側を二人で挟まれる形になる。
「まぁ〜〜〜っ!! なぁに、このつるつるのお肌っ!女として許せないわぁ! 」
「あら、よかったぁ。ムダ毛の処理もほとんどいらないわね。スレンダーだし、これなら露出の多いドレスも大丈夫そうっ」
「あ・・あのっ!? 」
「ねえ、あのコバルトブルーのベルベットドレスにしましょ!! メイクはピンクとモーヴ系でキュート&セクシーに行くわよ〜!!
」
「素敵〜〜っ!!! 」
「え・・・うわぁっ!!! 」
猛に口を挟む隙をまったく与えず、謎の女性二人はきゃあきゃあと大騒ぎしながら、きっかり1時間後には、呆然とする猛をドレスの似合う美人に変身させていたのだった。
「彼女達は、今回協力をお願いしたモデルプロダクションに所属する、ヘアメイクとファッションコーディネーターです」
「協力?」
不思議そうな猛に、桂が苦笑する。
「坂本警部のご親戚・・なんですよね?」
桂の言葉の最後の部分は坂本に向けられたものである。それにむっとした顔で、坂本が続けた。
「私の叔母がモデルプロダクションをやっていて、たまたま今夜のパーティーに行くと言っていたので、ちょっと協力をお願いしたのだ」
「有名なプロダクションですからね。もしかしてと思って伺ったら、本当に招待を受けていました。しかも所属モデルもご一緒にどうぞと言われているそうですから、これは渡りに船とばかりに、板橋くんを一緒に連れていってもらうようにお願いしたんです」
「え・・ええええっ!! 」
その時、坂本の携帯の着信音が車内に響いた。
「近くに着いたらしいぞ」
短い通話の後、言った坂本の言葉とほぼ同時にエンジン音が聞こえ、3人の乗る車から数十メートル離れたゲートが開き、一台の黒塗りの高級外車が薄暗い駐車場に入ってきた。
桂が車の外に出て合図をすると、その車は目の前まで来て静かに止まった。
運転手が降りてきて後部座席のドアを開けると、1人の女性がすっと降り立った。
「お久しぶりね。桂くん」
坂本の叔母に当たるその女性、水上綾は、桂の前に立つとにっこりと笑った。
はっきりとした性格が現れている美貌、そして自分も一流モデルであったことが容易に想像できる、美しくバランスの取れた身体には、チャコールグレーのパンツスーツに華やかなピンクのビスチェを合わせて、落ち着いているが鮮やかな雰囲気を醸しだしている。
「ご無沙汰してます、綾さん。今日はご無理を言って申し訳ありません」
「お安い御用よ。お礼なら今度うちでバイトってことでどう?」
「警察はバイト禁止なもので。お礼は今度、坂本警部がお食事にご招待するというのはどうでしょう?」
「う〜〜ん、三四郎さんと食事ねぇ・・今一つね・・桂くんも一緒ならいいわ」
「まてっ、桂っ!! 叔母様!! 二人で勝手に話を決めるなっ!!!」
坂本が慌てて二人の間に割ってはいると、綾はむっとした表情で振り向いた。
「もう三四郎さん、叔母様はやめてっていつも言ってるでしょ」
「私の母の妹なんだから叔母様でしょう?」
「そういうことじゃないのよ・・まぁ今更いいわ。それより私が連れて行くのはどの子?まさか三四郎さんじゃないわよね」
「当たり前です。板橋!こっちに来なさい」
ワンボックスカーの中から、ことの顛末をそっと伺っていた猛は、いきなりのご指名に飛び上がった。
「板橋?早く」
「は、はいっ!! 」
慌てて降りようとするが、慣れないドレスでどうにもうまく動けない。
何とか裾を踏まずに車から降りると、今度はヒールによろけながら3人の元に急いだ。
「この子・・ね」
綾は腕を組んだまま正面からじっと猛を見つめた。
『何だか睨まれてる・・?やっぱりこんな格好、絶対おかしいって・・!!』
猛が気まずい思いでうつむいた時、
「いいわ」
「は?」
綾がはっきりとした声で言った。思わず顔を上げた猛のあごを、爪をワインレッドに染めた細い指がクイッと持ち上げた。
間近に迫った綾の顔に気圧された猛は、身じろぎ1つできずにいる。
「合格よ。思ったよりも数倍可愛いく仕上がってるわ。男性といってももともと体の線が細めで綺麗だし、ドレスもうまく首から肩をカバーしてる。見た目は十分OKよ。うちにいるニューハーフのモデルと引けを取らないくらい綺麗ね」
『・・・あんまりうれしくない・・』
綾の言葉に、一気に力が抜けていく猛だった。だが、次の台詞に今度は本当に倒れそうになった。
「あとは歩き方と立ち方。そのままじゃとてもモデルには見えないわ。開場までに基本だけはここでしっかり覚えてもらいますからね」
「・・え、えええぇぇっ!!!」
そして、その後40分間、地下駐車場には綾の厳しい声と、猛の「はいっ」という返事が、まるで体育会系部活の練習のように響いていた・・・。
to be continued・・・
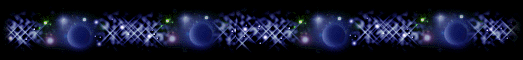
|