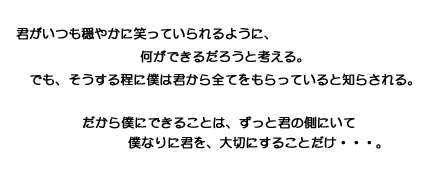特別な日には・・・。 (耕平さんお誕生日Ver.) ついこの間にも感じる今年の春先に、自分から同じ台詞を言った覚えがあった。
「来月の誕生日に何か欲しいものはあるか?」
猛の口から出たそんな言葉に、知らず自分の表情が弛んでしまうことを耕平は自覚する。
そう、あの時もこうして自分の部屋に猛がいて。
変わらず愛しいその存在が側にあることを、こんな時に実感できる。何にも代えがたく幸せで穏やかな時間を過ごしながら。「耕平!! 聞いてんのかよ、おいっ」
「ああ、聞いてるよ」
しびれをきらしたように、言う猛に耕平は答えた。夏休みも終盤にかかっている。猛も受験にそなえて今年の夏は忙しく過ごしていたが、こうして耕平に会いにくることだけは欠かしていなかった。
毎日二人きりでゆっくりと。という訳にはなかなかいかなかったが、それでも大切な時間を少しでもお互いの居る場所で過ごせることが嬉しい。今日も猛は少し部屋に顔を出しただけで、もう帰る準備を始めなければならなかった。物足りない気がしないではないが、大切な時期なだけにこれは二人ともが納得していることだ。
猛を見ていると以前とは違った意識の強さを感じられて、耕平はまたその変化を見ることが、また新しい猛を知ることが嬉しくなる。どこかで寂しさの様な感覚を覚えることもあるが、彼が、彼である限りすべてを大切に思うから、やはり嬉しいという言葉がこの感情にも相応しいのだろうと思う。
もうそうとう重症なのは最初から解っていたことではあるけれど、この存在に勝てるものではないことは最初から解っていたことだったから。そう、自覚した時の気持ちもこうしてずっと続いている。そして、それがまた愛しさに繋がっていくのだ。
−−−『来年からは一緒に暮らせる。』
これは今、二人が心の中で持っている同じ楽しみ。
その為にもと猛は毎日、しっかりと自分の足を地につけようとして頑張っているようでもあったのだ。「耕平?」
あまりに長く返事のない耕平に、苛立ちを通り越して心配になったのか、猛がすぐ側に来て少しだけ目線の下にあるその瞳で自分を覗き込んでいた。
間近にある、自分だけが映る大きな瞳。
「悪い。なんでもない」
その前髪を柔らかくかきあげてやりながら、そう返すと、少し安堵したように表情を揺らしてから、でも心配した表情を感じさせてしまったことを悟られたのもバツが悪いのか少し照れが感じられる怒ったような口調でまた口を開いた。「なんでもないなら、ぼけっとしてんなよ。そんで、何か欲しいもんはっ?」
「ん〜・・・」
少し挑みかかるような瞳をして真直ぐに自分を観ている表情に、いろいろと頭をめぐらせてみるが耕平にはこれといって欲しいものは思い浮かばない。別に、猛がいたら自分はそれでいい。
そう考えて、春先の事を思い出した。
そういえば、猛もしばらく考えて出してくれた一番の結論はこれだったのだ。自分がいれば、それでいいと。その時間が大切だと。
−−−なら、答えはひとつだ。
そう、猛がくれた答えを返せばいい。「何でもいいのか?」
「俺ができる範囲なら」
「じゃ、お前」
「え?」
「猛が欲しい」
とびきりの笑顔をそえて、言ってやったのだが・・・。「なっ///?!」
猛が一瞬言葉をつまらせたかと思うと、次の瞬間には「がしいっっ!」という盛大な音と共に耕平の頭部に思いきりの衝撃が襲っていた。
「な、なんで〜? 猛クン」
あまりに予想外の展開にそう泣きつく耕平を、仁王のような顔をして、けれど耳まで赤くした猛が睨んでいる。
「お前が変なこと言うからだろ!」
「この間はお前もそう言ったじゃないか。別に深い意味は・・・」
「お前が言うと洒落になんないんだよっ!!」
最後まで言わせずに、猛がたたみかけ、
「俺、帰るからなっ」
そのまま荷物をひっつかみ、痛む頭を押さえる耕平をしり目に猛はリビングを出て行こうとしてしまう。が。しかし。
ふと、立ち止まって間をおくと、猛が少し俯いたままの状態で耕平の側にずんずん戻ってきた。耕平はなりゆきに流されるまま突っ立っているだけだ。
「猛?」
どうしたのかと、その名を口にすると突然また猛の腕が自分に向かって伸びてくる。そして今度は思わず身を引いた耕平の襟首を掴み思いきり引き寄せたかと思うと、すぐ耳の側で一言言い捨てたのだ。「それは別口でいいよっ」
きっとひどくテレながらだろう。怒った時の声音そのままで投げ捨てるように言われた言葉が、耕平はすぐに理解は出来ない。
すぐ側で言われた所為で、耕平にはその表情も見えなかったけれど・・・。首まで真っ赤になっている猛の後ろ姿が今度こそさっさと廊下へと姿を消していく。
それが目には映ってはいたが、耕平はまだ動けずにいた。あまりに意外な言葉を返してくれた気がしたのだ。
この腕の中に抱き込んでしまいたい気持ちになった時も、言葉ではなくてもいつでも「嫌じゃないよ」と、そっと寄せてくれる身体で自分に対する気持ちを感じさせてくれた。決して積極的というわけではないけれど猛らしく伝えてくれる気持ちがいつも嬉しかった。
まだお互いが戸惑いながら、ようやく一緒に眠ることができるようになった頃からずっと・・・。少しずつ、少しずつ二人の関係が変わっていくのを感じる。それは決して嫌なことでも悲観するものでもなく。
起こる全てのことが自分達にとってはきっと必要な事なのだろうと思う。そして共に居られるなら、それがどんなことでも受け止めていけるのだろうとも・・・。
穏やかにおこっている変化をまたここでも感じながら、耕平はまだそこに立ちすくんでいた。「耕平っ、見送りもしないつもりかよっ」
そして、ようやっと玄関から聞こえる猛の声に我を取り戻した。きっと自分のこの動けない状態がわかってはいたのであろうちょっと我侭な恋人は、そんな言葉で呪縛を解き、甘えてくれる。
すっかりそれに振り回されている自分に気がつきながらも、それもとても嬉しい瞬間だということをこんな時にも感じられる。「・・・」
立ち直り、それでも顔に少しだけ締まりなさも感じながら、耕平は王子様の見送りに急いで足を向ける。リビングのドアをくぐって声の発生した方に目をやると、
何よりも大切な、その姿が自分を見上げていた・・・。
〜 Fin 〜